住宅を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
特に外装部分である屋根と外壁は、常に風雨や紫外線にさらされているため、適切な時期に塗装工事を行う必要があります。
では、屋根塗装と外壁塗装は同時に行うべきなのでしょうか?
それとも別々に行った方が良いのでしょうか?
この記事では、両者を同時に行うメリット・デメリットや費用相場について詳しく解説します。
Contents
屋根塗装と外壁塗装の役割
まずは、屋根塗装と外壁塗装がそれぞれどのような役割を持っているのかを理解することが大切です。
建物を保護する
屋根と外壁の最も重要な役割は、建物を外部環境から守ることです。
屋根塗装は、雨水や紫外線から屋根材を保護します。
特に、雨漏りを防ぐことは住宅の寿命を延ばすために非常に重要です。
屋根材の種類(スレート、瓦、トタンなど)によって劣化の進行速度は異なりますが、塗装によって防水性を高め、屋根材の劣化を遅らせることができます。
一方、外壁塗装の役割は、建物の構造体を雨や湿気から守り、カビやコケの発生を防止することです。
外壁は建物の顔とも言える部分で、適切に塗装することで紫外線による退色や、ひび割れによる雨水の侵入を防ぎます。
両方の塗装が適切に行われていることで、建物全体の耐久性が高まり、修繕費用の削減にもつながります。
見た目を良くする
塗装は保護機能だけでなく、住宅の美観を向上させる役割も担っています。
屋根塗装は、色あせや苔・藻の発生を防ぎ、常に清潔感のある見た目を維持します。
外壁塗装も同様に、色あせやチョーキング(粉状の白い物質が出る現象)を防ぎ、建物の美しさを保つのです。
カラーバリエーションも豊富で、住宅の雰囲気を一新できます。
屋根と外壁の色の組み合わせにより、住宅全体の統一感や調和を生み出せるのも魅力の一つです。
居心地の良い環境にする
塗装は見た目だけでなく、住環境の快適性にも影響します。
遮熱塗料や断熱塗料を使用することで、夏場の室内温度上昇を抑え、エアコンの使用頻度を減らすことができるのです。
これにより、省エネ効果が期待できるだけでなく、光熱費の削減にもつながります。
また、防音効果のある塗料を選ぶことで、外部からの騒音を軽減することも可能です。
特に、交通量の多い道路沿いや商業施設の近くでは、この効果が実感できるでしょう。
さらに、防カビ・防藻性能を持つ塗料を使用することで、健康的な住環境を維持できます。
特に、湿気の多い地域では、このような機能性塗料の効果が高くなります。
屋根塗装と外壁塗装を同時に行うメリット
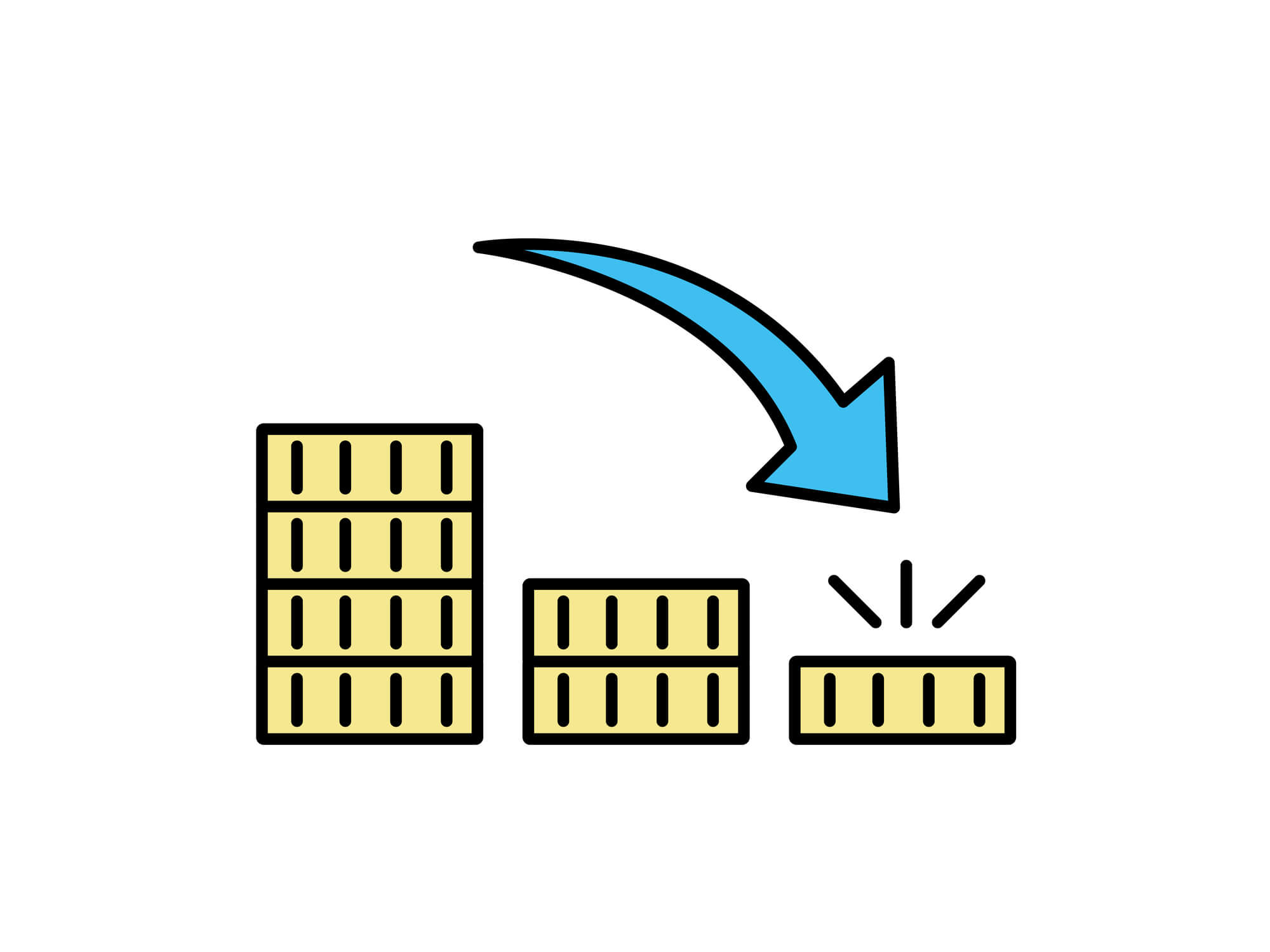
屋根塗装と外壁塗装を同時に行うことには、さまざまなメリットがあります。
施工コストを抑えられる
最も大きなメリットの一つが、コスト面での節約です。
屋根塗装と外壁塗装を別々に行うと、それぞれの工事で足場を組む必要があります。
足場の設置・撤去には多くの費用がかかるため、同時に工事を行うことで、この費用を一度で済ませられます。
足場代は、決して小さくない金額です。
同時施工によるこの節約効果は、一般的な住宅で10万円から30万円程度になることも珍しくありません。
また、屋根塗装と外壁塗装を同時に行うことで職人の移動費や諸経費なども一度で済みます。
そのため、総合的に見てコストパフォーマンスが高くなるのです。
塗装する際の手間が減る
工事を依頼する側にとっても、同時施工は手間を大幅に削減できるメリットがあります。
別々に工事を行う場合、それぞれの工事について業者選びから見積もり、打ち合わせ、工事期間中の対応まで、すべてのプロセスを二度行わなければなりません。
しかし、屋根塗装と外壁塗装を同時に行えば、これらの手続きが一度で済みます。
また、工事中は騒音や振動、粉塵などの影響があります。
これらの不便を一度に済ませられるのも大きなメリットと言えるでしょう。
見た目に統一感が出る
屋根と外壁の色のバランスは、住宅の外観の印象を大きく左右します。
同時に塗装することで、色調の統一感やデザインの一貫性を保つことができるのです。
例えば、落ち着いたグレーの屋根に対して、温かみのあるベージュやアイボリーの外壁を組み合わせるなど、全体のバランスを見ながら色選びができます。
また、同じ系統の色で統一することで、洗練された印象の住宅に仕上げることも可能です。
別々に工事を行うと、最初に塗装した部分の色が実際に塗装された後の色と想像していた色が異なる場合があります。
その結果、後から塗装する部分との調和が難しくなってしまうのです。
自由に塗料色を選択できる
同時施工のもう一つのメリットは、塗料選びの自由度が高まる点です。
屋根と外壁の塗料は、それぞれに適した種類がありますが、同時に選ぶことで組み合わせを考慮した選択ができます。
例えば、屋根に高耐久性の塗料を使用し、外壁は防汚性の高い塗料を選ぶなど、住宅全体としての機能性を考慮した選択が可能です。
また、色だけでなく、光沢の有無や質感なども考慮して選ぶことができます。
そのため、より細やかなデザイン調整ができるのです。
屋根塗装と外壁塗装を同時に行うデメリット

メリットがある一方で、同時施工にはいくつかのデメリットも存在します。
デメリットを把握した上で、同時施行を行いましょう。
まとまった予算が必要になる
同時施工の最大のデメリットは、一度に大きな出費が必要になる点です。
一般的な戸建て住宅の場合、屋根塗装と外壁塗装を同時に行うと、合計で100万円から200万円程度の費用がかかることが多いです。
これは家計にとって大きな負担となるため、資金計画をしっかり立てる必要があります。
別々に行えば、数年の間隔を置いて費用を分散できますが、同時施工ではそれができません。
ただし、リフォームローンなどの活用により、月々の支払いを軽減する方法もあります。
工期が長くなる
同時施工は当然ながら、屋根だけ、または外壁だけの塗装と比べると工期が長くなります。
通常、外壁だけの塗装であれば7日から10日程度、屋根だけの塗装であれば3日から5日程度で完了することが多いですが、同時施工の場合は10日から14日程度かかることが一般的です。
この間は、足場が組まれ、塗料の臭いや騒音などの不便が続きます。
また、天候不良により工期が延びることもあるため、余裕を持ったスケジュール調整が必要です。
特に、梅雨時期や台風シーズンは予定通りに進まないリスクが高くなります。
屋根と外壁の劣化状況が異なる場合がある
住宅の屋根と外壁は、必ずしも同じペースで劣化するわけではありません。
屋根は直射日光や雨水の影響を強く受けるため、外壁よりも早く劣化することが多いです。
逆に、日当たりの悪い北側の外壁は、湿気によるカビやコケの発生が多く見られるなど、部位によって劣化の進行度合いは異なります。
このような場合、まだ塗り替えが必要ない部分まで同時に塗装することになり、効率が悪いと感じることもあるでしょう。
ただし、予防的な観点から見れば、早めの塗装が結果的に建物の寿命を延ばすこともあります。
屋根と外壁の劣化サイン
適切な塗装時期を見極めるためには、劣化のサインを知っておくことが重要です。
屋根塗装の劣化サイン
屋根材の種類によって劣化の進行度合いや見た目の変化は異なりますが、一般的な劣化サインとしては以下のようなものがあります。
| サイン | 詳細 |
|---|---|
| 色あせ・変色 | 塗膜が劣化すると、元の色から褪せたり、くすんだりします。 特に、南側の屋根は紫外線の影響で色あせが早く進行します。 |
| コケやカビの発生 | 屋根の表面にコケやカビが発生すると、見た目が悪くなるだけでなく、屋根材の劣化を早める原因にもなります。 |
| チョーキング現象 | 屋根を手で触ると白い粉が付くようになる現象です。 塗膜が紫外線によって分解され、表面が粉状になっている状態を指します。 |
| ひび割れ・欠け | スレート屋根などでは、経年劣化によりひび割れや欠けが生じることがあります。 これにより雨水が侵入しやすくなり、漏水の原因になります。 |
| 反り・めくれ | トタン屋根などでは、熱による膨張収縮の繰り返しにより、反りやめくれが発生することがあります。 |
これらのサインが見られる場合は、屋根塗装を検討する時期と言えます。
特に複数のサインが同時に見られる場合は、早めの対応が望ましいです。
外壁塗装の劣化サイン
外壁も屋根と同様に、さまざまな劣化サインが現れます。
| サイン | 詳細 |
|---|---|
| チョーキング現象 | 外壁を手で触ると白い粉が付く状態です。 屋根と同様に、塗膜が紫外線で分解されている状態を示しています。 |
| 色あせ・変色 | 特に日当たりの良い南面や西面で顕著に現れます。 元の色から著しく変化している場合は、塗装の検討時期です。 |
| クラック(ひび割れ) | モルタル外壁やサイディングの目地部分にひび割れが生じることがあります。 小さなひび割れでも放置すると雨水が侵入し、下地の劣化を招きます。 |
| カビ・コケの発生 | 北面など日当たりの悪い場所や湿気の多い場所に発生しやすいです。 見た目の問題だけでなく、外壁材自体の劣化も促進します。 |
| 塗膜の浮き・はがれ | 塗膜が部分的に浮き上がったり、はがれたりする現象です。 下地が露出すると急速に劣化が進行します。 |
| シーリングの劣化 | 窓周りやサイディングの目地などのシーリング(コーキング)が硬化してひび割れたり、はがれたりしている場合は注意が必要です。 |
これらのサインが複数見られる場合は、外壁塗装を検討する良いタイミングと言えるでしょう。
一般的に、外壁塗装の目安は10年前後と言われていますが、環境や外壁材の種類によって異なります。
屋根塗装と外壁塗装を同時に行う際の工事の流れ
屋根塗装と外壁塗装を同時に行う場合の一般的な工事の流れは、以下の通りです。
| 流れ | 詳細 |
|---|---|
| 現地調査・見積もり | 業者が現地を訪れ、屋根と外壁の状態を確認し、必要な工事内容と費用を見積もります。 |
| 契約・色決め | 工事内容と費用に合意したら契約を行います。 この際に屋根と外壁の色や塗料の種類を決定します。 カラーサンプルなどを参考にして慎重に選びましょう。 |
| 足場の設置 | 工事の安全性を確保するために、建物の周囲に足場を組みます。 |
| 高圧洗浄 | 屋根と外壁の汚れやコケ、古い塗膜の浮いた部分などを高圧洗浄機で洗い流します。 この工程により塗料の密着性が高まります。 |
| 下地処理 | クラック(ひび割れ)や欠損部分の補修、サイディングの目地やコーキングの打ち替えなどを行います。 下地処理が不十分だと、新しい塗装の仕上がりや耐久性に影響します。 |
| 養生作業 | 塗装しない部分(窓ガラス、ドア、植栽など)に養生を施し、塗料が付着しないようにします。 |
| 下塗り | 下塗り用の塗料(プライマー)を塗布します。 これにより塗料の密着性が高まり、仕上がりの美しさや耐久性が向上します。 |
| 中塗り・上塗り | 本塗装として中塗りと上塗りを行います。 均一な仕上がりと十分な塗膜の厚さを確保します。 |
| シーリング工事 | 窓周りや外壁の目地などのシーリング(コーキング)を打ち替えます。 |
| 完了検査・清掃 | 工事の仕上がりを確認し、不備があれば修正します。 周囲の清掃を行い、養生を取り外します。 |
| 足場解体 | 全ての作業が完了したら足場を解体します。 |
| 最終確認・引き渡し | 施主立会いのもと最終確認を行い、工事完了となります。 |
工事期間は住宅の大きさや形状、天候などによって異なりますが、一般的な戸建て住宅で10日から14日程度が目安です。
天候不良により工期が延びることもあるため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
塗料の種類により寿命と特徴が異なる
塗料の種類によって耐久性や機能性、費用が大きく異なります。
主な塗料の種類と特徴を見ていきましょう。
アクリル樹脂系
最も基本的な塗料で、価格も比較的安価です。
| 耐久年数 | 5年〜8年程度 |
|---|---|
| コスト | 低価格(他の塗料と比較して最も安い) |
| 特性 | 施工性が良く、乾燥が早い |
賃貸物件や短期間での売却予定がある住宅など、コストを抑えたい場合に適しています。
ただし、耐久性が低いため、頻繁な塗り替えが必要です。
ウレタン樹脂系
アクリル樹脂よりも耐久性が高く、一般住宅でよく使用される塗料です。
| 耐久年数 | 8年~10年程度 |
|---|---|
| コスト | 中程度 |
| 特性 | 弾力性があり、微細なひび割れに対応可能 |
一般的な戸建て住宅の外壁に適しています。
コストパフォーマンスが良く、バランスの取れた塗料です。
アクリルシリコン樹脂系(シリコン系)
近年、最も一般的に使用されている塗料の一つです。
| 耐久年数 | 10年~15年程度 |
|---|---|
| コスト | 中〜高程度 |
| 特性 | 耐候性・耐水性に優れ、汚れにくい |
長期間のメンテナンス費用を考慮すると、多くの住宅でコストパフォーマンスが高いと評価されています。
特に、汚れが付きやすい環境にある住宅に適した塗料です。
フッ素樹脂系
高耐久な塗料の一つで、長期間美観を保ちたい場合に適しています。
| 耐久年数 | 15年~20年程度 |
|---|---|
| コスト | 高価格 |
| 特性 | 非常に高い耐候性・耐汚染性、色褪せが少ない |
長期にわたって住み続ける予定の住宅や、高級住宅、マンションなどに適しています。
初期コストは高いですが、塗り替え頻度が少なくなるため、長期的に見るとコスト効率が良いです。
光触媒塗料
太陽光や照明の光を受けると化学反応を起こし、さまざまな機能を発揮する新しいタイプの塗料です。
| 耐久年数 | 20年程度 |
|---|---|
| コスト | 高価格 |
| 特性 | 空気浄化作用、防汚性、抗菌性などの機能を持つ |
環境への配慮や健康面を重視する住宅、大気汚染の多い都市部の住宅などに適しています。
無機塗料
セラミックなどの無機物を主成分とした塗料で、非常に高い耐久性を持ちます。
| 耐久年数 | 20年~25年程度 |
|---|---|
| コスト | 非常に高価格 |
| 特性 | 超高耐久、防火性能が高い |
超長期的な視点で考える場合や、特に防火性能を重視する場合に適しています。
非常に高価ですが、それに見合う性能を持っているのが特徴です。
屋根塗装と外壁塗装を同時に行う際の費用相場
屋根塗装と外壁塗装を同時に行う場合の費用相場を見ていきましょう。
坪数・塗装面積ごとに、およその費用相場を示します。
| 坪数 | 塗装面積 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 20坪 | 約79㎡ | 60万円~130万円程度 |
| 30坪 | 約119㎡ | 80万円~140万円程度 |
| 40坪 | 約158㎡ | 100万円~170万円程度 |
| 50坪 | 約198㎡ | 120万円~190万円程度 |
| 60坪 | 約238㎡ | 140万円~240万円程度 |
費用は住宅の立地条件や形状、塗装面積、既存の塗膜の状態などによっても変動します。
例えば、3階建ての住宅や複雑な形状の屋根は、標準的な住宅よりも費用が高くなる傾向があります。
また、地域によっても相場に差があり、都市部では地方よりも人件費が高いため、全体的に費用が高くなる傾向があります。
ただし、屋根塗装と外壁塗装を別々に行う場合と比較すると、同時施工では足場代や諸経費などが一度で済むため、トータル費用は削減できます。
屋根塗装と外壁塗装のコストを抑える方法

塗装工事は決して安い買い物ではありません。
しかし、いくつかの方法を使ってコストを抑えることができます。
火災保険を活用する
自然災害による屋根や外壁の損傷があれば、火災保険の補償対象になる可能性があります。
台風や雹、雪などの自然災害で屋根材や外壁材が損傷した場合、加入している火災保険の補償内容によっては、修繕費用の一部または全部が保険金として支払われます。
ただし、経年劣化による損傷は補償対象外となるため、自然災害との因果関係を明確にしなければいけません。
保険申請の際は、専門の調査員による現地調査が行われることが一般的です。
保険を活用する際は、保険会社への申請方法や必要書類について事前に確認しておくことをおすすめします。
また、申請をサポートしてくれる塗装業者もあるため、相談してみると良いでしょう。
補助金を活用する
地方自治体によっては、住宅リフォームに対する補助金制度を設けている場合があります。
省エネ性能の向上を目的とした塗装工事や、耐震性能の向上を伴うリフォーム工事に対して、補助金が出る自治体もあります。
また、特定の地域や歴史的な街並みの保全を目的とした外観リフォームに対する助成金制度もあるかもしれません。
補助金制度は自治体によって内容や条件が大きく異なります。
そのため、住んでいる市区町村の公式サイトや窓口で最新情報を確認するのがおすすめです。
塗料のグレードを下げる
全体的な費用を抑えるためには、塗料のグレードを調整するという方法もあります。
例えば、北側の外壁など目立たない部分や、劣化の進行が遅い部分には比較的安価なウレタン系塗料を使用し、南側の外壁や屋根など紫外線の影響を強く受ける部分には耐久性の高いシリコン系やフッ素系塗料を使用するといった方法があります。
ただし、極端に安い塗料を選ぶと早期に再塗装が必要になる可能性があるため、長期的なコスト面でのバランスを考慮することが大切です。
相見積もりを依頼する
複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を把握し、コストを抑えることができます。
一般的に、3社以上の業者から見積もりを取るのがおすすめです。
その際、単に価格だけでなく、使用する塗料の種類や品質、工事内容の詳細、アフターサービスなども比較しましょう。
見積もり内容に大きな差がある場合は、なぜそのような差が生じているのかを各業者に確認することで、不要な工程や過剰な見積もりを見極めることができます。
豊富な実績を持つ業者を選ぶ
信頼できる実績のある業者を選ぶことで、手戻りや追加工事の発生を防ぎ、結果的にコストを抑えることができます。
施工実績が豊富な業者は、効率的な作業計画を立てることができるため、工期が短縮され、人件費などのコストダウンにもつながるでしょう。
また、技術力の高い業者であれば、下地処理をしっかり行い、塗膜の耐久性を高められるため、長期的に見ればメンテナンス頻度が少なくなり、コスト削減になります。
業者選びの際は、施工事例や口コミ評価を確認したり、過去の施工物件を実際に見せてもらったりしましょう。
アフターフォロー体制がしっかりしている業者を選ぶことも重要なポイントです。
まとめ
屋根塗装と外壁塗装を同時に行うか、別々に行うかの判断は、住宅の状況や予算、ライフプランによって異なります。
塗装のタイミングを逃すと、屋根材や外壁材自体の劣化が進行し、大規模な修繕が必要になってしまうのです。
定期的な点検を行い、劣化のサインを見逃さないようにしましょう。
また、業者選びは相見積もりを取り、施工実績や保証内容、アフターフォローなども含めて総合的に判断するのがおすすめです。



