屋根は、日々紫外線や雨風から私たちを守ってくれます。
その屋根も経年劣化からは逃れられません。
劣化を放置すれば、雨漏りや建物の躯体へのダメージにつながる可能性があり、そうなると大規模な修繕が必要になってしまいます。
そうなる前に検討したいのが「屋根塗装」です。
屋根塗装は、屋根材を保護し、美観を回復させ、住まいの寿命を延ばすために非常に重要なメンテナンスです。
しかし、専門的な知識が必要な工事だからこそ、「どの業者に頼めばいいのかわからない」「費用はどれくらいかかるのか」「失敗しないためには何に気をつければいいのか」といった不安や疑問を抱える方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、屋根塗装を検討している方のために、屋根塗装がどのような工程で進められるのか、工事を依頼する際に押さえておくべき注意点、そして最も重要な「失敗しない業者選びのポイント」まで詳しく解説します。
屋根塗装に関する不安が解消され、自信を持って大切な住まいのメンテナンスを進めるための知識が身につくため、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
屋根劣化で起こる症状
屋根塗装を検討する最初のステップは、自宅の屋根の状態を把握することです。
ここでは、専門家でなくても比較的判断しやすい、代表的な劣化の症状を4つ紹介します。
これらのサインを見つけたら、メンテナンスを検討しましょう。
色褪せ
新築時や前回の塗装から時間が経つと、屋根の色が全体的に薄くなったり、斑になったりする「色褪せ」が起こります。
これは、屋根の表面を保護している塗膜が、主に太陽の紫外線によって劣化している最も初期のサインです。
塗料には、屋根材を紫外線や雨水から守る機能がありますが、色褪せが起きているということは、その保護機能が低下し始めている証拠です。
特に、日当たりの良い南側の屋根面は色褪せが進行しやすい傾向にあります。
色褪せに気づいた時点が、そろそろ次の塗り替えを検討し始める良いタイミングと言えるでしょう。
ひび割れ
屋根材の表面に髪の毛のような細い線や、よりはっきりとした亀裂が入るのが「ひび割れ(クラック)」です。
スレート屋根やセメント瓦でよく見られる症状です。
ひび割れは、塗膜の劣化がさらに進み、屋根材自体が紫外線や温度変化による伸縮に耐えられなくなって発生します。
小さなひび割れだからと油断してはいけません。
そのわずかな隙間から雨水が浸入し、屋根材の内部にまで水が回り込んでしまうからです。
浸入した水分は、屋根材を脆くさせ、冬場には凍結してひび割れをさらに大きくする「凍害」を引き起こす原因にもなります。
ひび割れが屋根材の広範囲に及ぶと、塗装だけでは補修が難しくなり、屋根材の交換やカバー工法といったより大掛かりな工事が必要になる可能性も出てきます。
小さなひび割れのうちに、専門家による診断と適切な処置を施すことが重要です。
コケの付着
屋根の表面に緑色のコケや、黒っぽいカビ、藻などが付着している状態も、劣化が進行しているサインです。
これらは、塗膜の防水性が失われ、屋根の表面が常に湿った状態になっているために発生します。
特に、日当たりの悪い北側の屋根面や、近隣に川や林がある湿度の高い環境で発生しやすくなります。
コケやカビは、その根から水分を吸収し、常に屋根材を湿らせた状態に保ちます。
この水分が屋根材の劣化をさらに加速させ、屋根材自体を脆く、弱くしてしまうのです。
また、コケが堆積すると水の流れが妨げられ、本来排出されるべき雨水が屋根に滞留し、雨漏りの直接的な原因となることも少なくありません。
美観を大きく損なうだけでなく、屋根材の寿命を著しく縮めてしまうため、コケの発生は放置せずに早めに対処してください。
反りや欠け
スレート屋根でよく見られるのが、屋根材の端が弓なりに反り上がる「反り」や、角が割れてしまう「欠け」です。
これらは、長年にわたって屋根材が水分を吸収・乾燥を繰り返すことで、素材が伸縮し、変形してしまう現象です。
屋根材に反りが生じると、屋根材同士の間に隙間ができます。
この隙間から強風時に雨水が吹き込みやすくなり、下地である防水シートや板を傷める原因となります。
また、反りが大きくなると、台風などの強風で屋根材が飛ばされたり、割れたりするリスクも高まります。
欠けに関しても同様で、欠けた部分から雨水が浸入する可能性があります。
これらの症状は、塗膜の保護機能が完全に失われ、屋根材自体がダメージを受けている証拠です。
劣化が著しい場合は、塗装によるメンテナンスでは対応できません。
一部の屋根材の差し替えや、屋根全体を新しい屋根材で覆う「カバー工法」、あるいは屋根材をすべて交換する「葺き替え工事」が必要となるケースもあります。
屋根塗装の工程
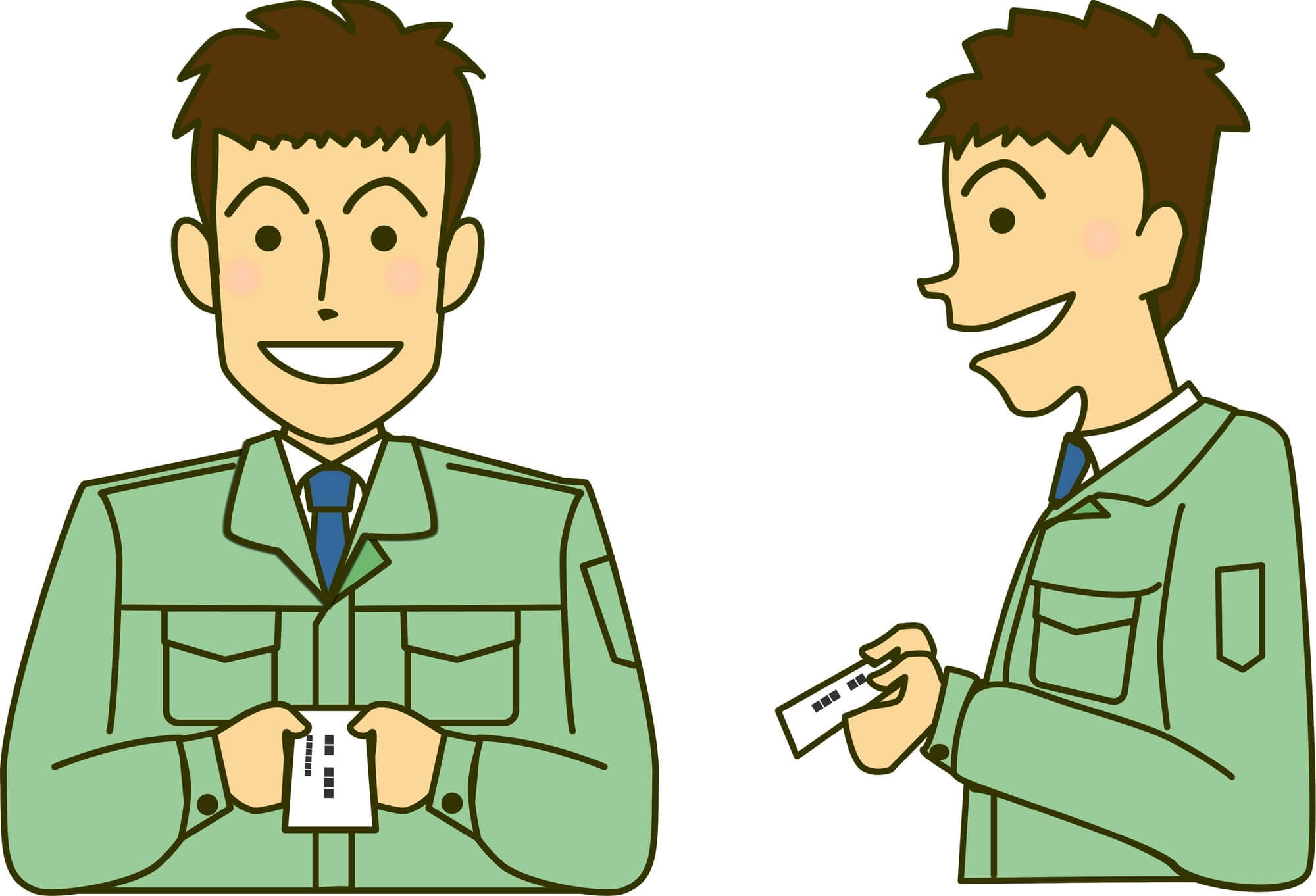
屋根塗装は、実際にどのような流れで進められるのでしょうか。
ここでは、一般的な屋根塗装の全11工程について順を追って詳しく解説します。
各工程が持つ意味と重要性を理解することで、手抜き工事を見抜く目も養われます。
1.近隣挨拶
工事を始める前に、まず施工業者が施主様と一緒に近隣のお宅へ挨拶に伺います。
これは、工事期間中に発生する騒音や塗料の臭い、工事車両の出入りなどについて事前に説明し、ご理解とご協力を得るための非常に重要な工程です。
工事が始まってから「聞いていない」という事態になると、近隣トラブルに発展しかねません。
丁寧な挨拶は、スムーズな工事進行と良好なご近所付き合いを維持するために不可欠です。
2.現場確認
挨拶が済んだら、工事開始前に再度、現場の最終確認を行います。
図面や見積書と照らし合わせながら、塗装する範囲、使用する塗料の色や種類、足場を設置する場所、障害物の有無などを改めてチェックします。
この段階で、施主様と施工業者の間で認識の齟齬がないか最終的にすり合わせを行います。
例えば、塗装しない箇所(窓や植木など)の確認や、工事車両の駐車スペース、職人のトイレの使用など、細かい点まで確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
3.足場の設置
安全な作業環境の確保と、作業品質の向上のために、建物の周囲に足場を組み立てます。
そして、足場の外側を「飛散防止ネット」で覆います。
足場は、職人が高所で安全に作業を行うための命綱であると同時に、安定した体勢で丁寧に塗装作業を行うための土台です。
足場がなければ、十分な高圧洗浄や細部の塗装ができず、品質の低下に直結します。
また、飛散防止ネットは、高圧洗浄時の水しぶきや、塗料が近隣の建物や車に飛散するのを防ぐ重要な役割を果たします。
4.高圧洗浄
足場の設置が完了したら、業務用の高圧洗浄機を使って屋根の汚れを徹底的に洗い流します。
長年の間に付着したコケやカビ、藻、ホコリ、剥がれかけた古い塗膜などを強力な水圧で除去します。
この高圧洗浄は、塗装の仕上がりを左右する極めて重要な工程です。
なぜなら、屋根に汚れや古い塗膜が残ったまま塗装をしても、新しい塗料が屋根材にしっかりと密着せず、数年で剥がれてしまう原因になるからです。
洗浄後は、屋根を完全に乾燥させるため、天候にもよりますが1日〜2日程度の乾燥期間を設けます。
5.下地処理
高圧洗浄と乾燥が終わったら、塗装する前に屋根材の補修を行う「下地処理」に入ります。
この工程も塗装の耐久性に直結する重要な作業です。
具体的には、スレート屋根のひび割れをコーキング材で埋めたり、金属屋根のサビをケレン(ヤスリや電動工具で削り落とす作業)で除去したりします。
瓦のズレや割れがあれば、この段階で補修・交換します。
どれだけ高価で高性能な塗料を使っても、その下地がガタガタの状態では意味がありません。
下地処理が不十分だと、補修箇所から再び劣化が始まったり、サビが再発したりして、塗装が早期にダメになってしまいます。
この下地処理をどれだけ丁寧に行うかが、職人の技術と業者の誠実さを見極めるポイントの一つです。
6.養生作業
塗装をしない箇所に塗料が付着しないように、ビニールシートやマスキングテープで保護する作業を「養生」と呼びます。
窓ガラスやサッシ、玄関ドア、植木、給湯器、そして近隣に駐車されている車など、塗料で汚れてはいけない部分を丁寧に覆っていきます。
この養生が雑だと、塗装のラインがガタガタになったり、思わぬ場所に塗料が付着してしまったりと、仕上がりの美観を大きく損ないます。
細かい部分までしっかりと、隙間なく養生を行う丁寧さが求められる工程です。
7.下塗り
いよいよ塗装工程に入ります。
最初に行うのが「下塗り」です。
下塗りには、その後に塗る中塗り・上塗り塗料を屋根材にしっかりと密着させる「接着剤」のような役割と、屋根材が塗料を吸い込みすぎるのを防ぐ役割があります。
屋根材の種類や劣化状況に合わせて、最適な下塗り材(シーラー、プライマー、フィラーなど)を選定します。
例えば、劣化が激しく吸い込みが強い屋根には、吸い込みを止める効果のある下塗り材を使用します。
この下塗りを省略したり、不適切な塗料を使ったりすると、塗膜の早期剥離や色ムラの原因となります。
完成後には見えなくなってしまう部分ですが、塗装の寿命を決める非常に重要な工程です。
8.中塗り
下塗りが完了し、十分に乾燥させたら、次に「中塗り」を行います。
中塗りは、仕上げの色を付ける上塗り材と同じ塗料を使用して塗装します。
中塗りには、下塗りと上塗りの間に塗膜の層を作ることで、全体の厚みを確保し、塗料が持つ本来の性能(防水性、耐久性など)を十分に発揮させるという重要な目的があります。
また、上塗りだけでは発色しにくい色をきれいに出したり、塗りムラを防いだりする役割も担っています。
塗装工事は基本的に「下塗り・中塗り・上塗り」の3回塗りが基本です。
工程を省いて中塗りをしない悪徳業者も存在するため、見積書や作業報告で工程が守られているかしっかり確認することが大切です。
9.上塗り
塗装工程の最後を飾るのが「上塗り」です。
中塗りと同じ塗料をもう一度塗り重ね、仕上げていきます。
上塗りは、屋根塗装の最終仕上げであり、美観を決定づける工程です。
塗りムラや塗り残しがないように、細心の注意を払って丁寧に塗装します。
また、紫外線や雨風といった外的要因から屋根を直接保護する最も重要な層となるため、規定の塗布量を守り、均一な厚さの塗膜を形成することが求められます。
この3回の塗り重ねによって、初めて塗料メーカーが想定する耐久性や機能性が発揮されるのです。
10.最終確認と手直し
すべての上塗り作業が完了したら、業者による自主検査が行われます。
塗り残しや色ムラはないか、塗料の飛散はないか、養生を剥がした後のラインは綺麗かなど、細部にわたって厳しくチェックします。
このチェックで不備が見つかった場合は、手直しを行います。
そして、業者のチェックが終わった後、施主様立ち会いのもとで最終確認を行います。
気になる点があれば、この段階で遠慮なく指摘し、納得がいくまで説明や手直しをしてもらうことが重要です。
すべての確認が完了し、施主様が納得して初めて工事完了となります。
11.足場の解体と清掃
施主様の最終確認が完了したら、設置していた足場を解体し、撤去します。
その際、建物の周りにゴミや廃材が落ちていないかを確認し、敷地内や周辺道路の清掃を丁寧に行います。
近隣への配慮を忘れず、工事前よりもきれいな状態にして現場を去るのが、信頼できる業者の証と言えるでしょう。
屋根塗装での注意点
屋根塗装を成功させるためには、工事の工程だけでなく、いくつか事前に知っておくべき注意点があります。
これらを押さえておくことで、予期せぬトラブルや失敗を防ぐことができます。
塗り替えの回数は基本的に3回まで
屋根塗装は無限に繰り返せるわけではなく、一般的に3回が限度とされます。
塗装を重ねると塗膜の総重量が増し、地震の揺れなどで屋根材ごと剥がれる危険性が高まるためです。
また、古い塗膜の上に重ねることで密着性も低下します。
複数回塗装済みの屋根は、塗装以外のカバー工法や葺き替えを検討する必要があると覚えておきましょう。
塗装前に屋根材の劣化状況を確認
塗装は屋根材の表面を保護する処置であり、屋根材自体の深刻な劣化は直せません。
例えば、広範囲のひび割れや下地の腐食が進んでいる場合、塗装をしても雨漏りは止まらないのです。
優良業者は塗装前に必ず屋根の状態を診断し、塗装が適切か、あるいはカバー工法や葺き替えが必要かを的確に判断してくれます。
塗装後も定期的なメンテナンスを実施
高品質な塗装をしても「それで終わり」ではありません。
台風などの自然災害で不具合が生じることもあります。
塗装の保護機能を長持ちさせ、住まいの寿命を延ばすため、塗装後も専門家による定期点検が不可欠です。
小さな異常を早期に発見・補修することで、結果的に将来の大規模な修繕費を抑えることにつながります。
失敗しない業者選びのポイント

屋根塗装の成否は、業者選びで9割決まると言っても過言ではありません。
数多くの塗装業者の中から、信頼できるパートナーを見つけ出すための3つの重要なポイントを解説します。
施工実績を確認する
業者を選ぶ際は、まず施工実績を確認しましょう。
特に、自宅と同じ屋根材の経験が豊富かは重要なポイントです。
業者のサイトで施工事例の写真を見る際は、単に綺麗になった結果だけでなく、作業工程が丁寧に公開されているかにも注目しましょう。
誠実な業者は仕事に自信があるため、作業内容を隠しません。
評価や口コミを確認する
Googleマップや専門サイトの口コミは業者の評判を知る手がかりになります。
ただし、良い評価ばかりの業者は注意も必要です。
注目すべきは「見積もりの説明が丁寧だった」など、具体的な内容が書かれているリアルな声です。
実際に利用した人でなければ書けないような具体的な口コミは、その業者の信頼性を判断するうえで非常に参考になります。
アフターサービスの有無を確認する
万が一の施工不良に備え、アフターサービスの有無と内容を契約前に必ず確認しましょう。
優良業者の多くは、独自の「自社保証(施工保証)」を設けています。
保証期間の長さだけでなく、どのような不具合が対象になるのか、保証書で内容をしっかり確認することが重要です。工
事後の定期点検の有無も、業者の信頼性を見極めるポイントです。
まとめ
屋根塗装は家の寿命を延ばす重要なメンテナンスです。
成功の鍵は、正しい知識を持ち、信頼できる業者を選ぶことです。
劣化のサインを見逃さず、本記事で解説した工程や注意点を参考に、大切な住まいを守る納得のいく屋根塗装をしましょう。



