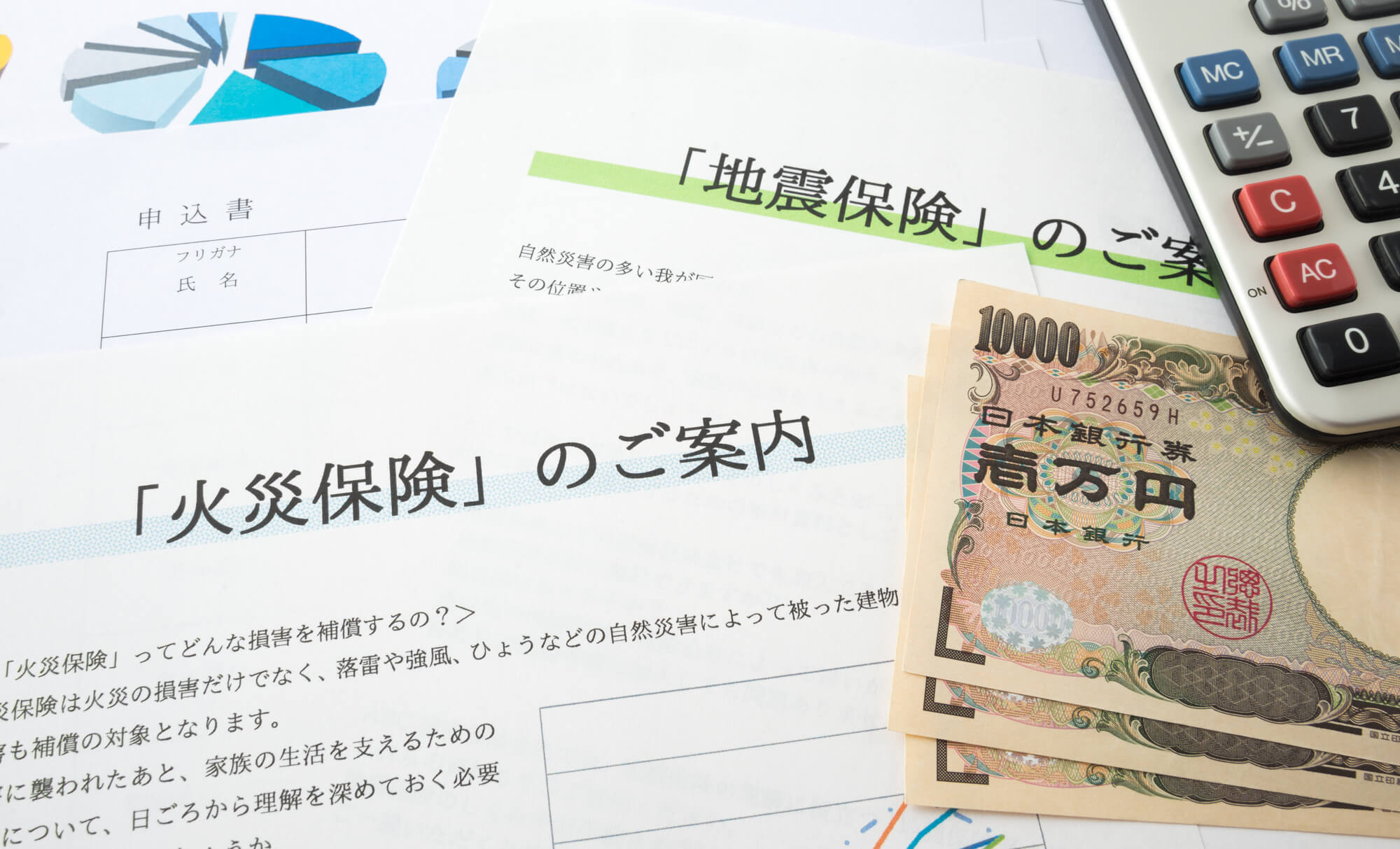屋根から雨漏りが発生する原因としては、屋根本体が老朽化して穴が空いているケースや屋根を構成するパーツが痛んで発生するのがほとんどです。
一度雨漏りが発生すると、早めに対処しなければ傷んだ箇所が広がり大掛かりな補修が必要になります。
雨漏りでは、火災保険が適用されると聞いたことがあっても、実際どのような条件下で適用されるのか分かりにくいものです。
ここでは、雨漏り修理で火災保険が適用される条件や、火災保険の申請の流れについてなど解説します。
屋根に雨漏りが発生する原因

屋根の雨漏りが発生する原因としては、次のようなことが考えられます。
屋根材の経年劣化による雨漏り
屋根材は365日外気に晒されているので、年々少しずつダメージが蓄積され経年劣化していきます。
近年よく利用されているコロニアル屋根なども、経年劣化により水を浸透させることがあるので、雨漏りの原因にもなります。
外的要因で屋根に穴が空いたことによる雨漏り
台風などの強風で飛んできたものにより穴が空いた場合や、地震で屋根が割れて穴が空いた場合なども雨漏りが発生します。
一度穴が空いたりヒビ割れが発生すると、すぐに塞がないと更に欠損箇所が広がる恐れがあります。
雨仕舞板金の劣化による雨漏り
屋根や屋根周辺には、建物の中に雨が侵入しないよう適切に排水する設備として「雨仕舞」という仕組みが施されています。
雨仕舞は一般的に板金でできていることが多く、定期的なメンテナンスを行わないと経年劣化により穴が空き雨漏りが発生する原因となります。
ルーフィングからの雨漏り
ルーフィングとは、板金や屋根本体などに敷く下葺き材のことを指します。
前述のような原因で雨漏りがしても、ルーフィングが適切に機能していると雨漏りは発生しません。
一般的にルーフィングの耐久年数は20年程度なので、建築後20年以上経過しているのであれば見直す必要があります。
雨漏り修理で火災保険が適用される条件
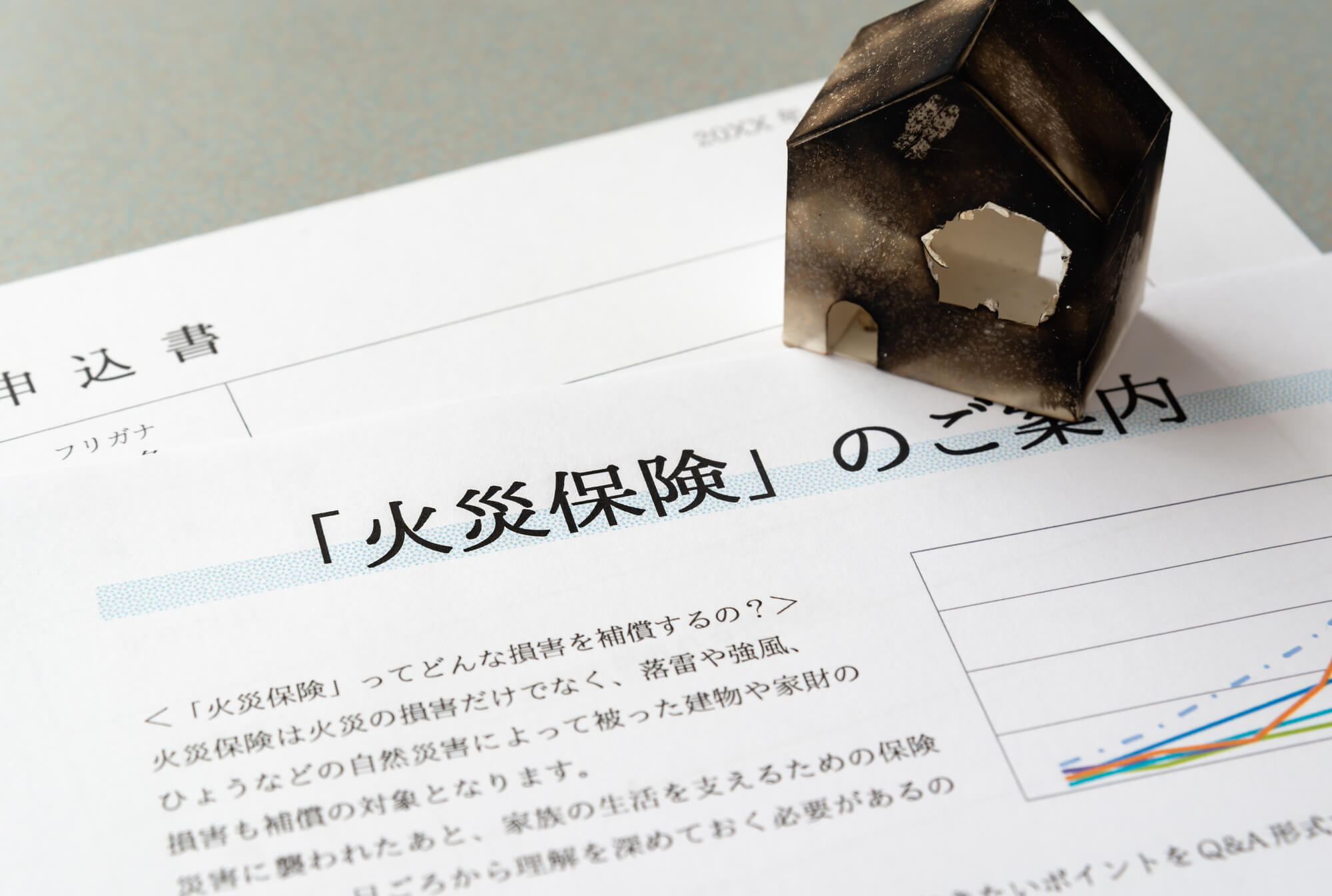
雨漏り修理で火災保険が適用される条件としては、第一に「自然災害による雨漏り」であることが重要となります。
前述の原因の中にある経年劣化によるものや、人的被害によるものなどは適用されません。
雨漏り修理で火災保険が適用される条件は以下の3点の場合となります。
- 風災
- 雪災
- 雹災
なお、以下でご紹介する条件は火災保険が一般的に適用されたケースであり、全てが100%保証されるわけではありません。
最終的には、保険会社が現場調査を行った上で、被害状況により判断します。
火災保険が適用されるケース①風災
火災保険が適用されるケースのベースは、前述の通り自然災害であることです。
自然災害の中で、台風による強風や突風、暴風や竜巻などによる被害が適用されます。
具体的な被害例としては次のようなものがあります。
風災による被害例
風災による被害例としては、以下のような例があります。
- 台風による強風で、飛来物が屋根に当たり破損することでの被害
- 台風で雨どいが破損することでの被害
- 竜巻で飛んできた屋根瓦が当たることでの被害
- 竜巻で飛んできた看板で屋根が破損することでの被害
火災保険が適用されるケース②雪災
大雪や、大雪による雪崩などによる被害も火災保険の適用範囲になります。
具体的な被害例としては次のようなものがあります。
雪災による被害例
雪災による被害例としては、以下のような例があります。
- 屋根に大雪が積もり、雪の重みによる被害
- 雪解け水による被害
- 積雪が落下することでの被害
火災保険が適用されるケース③雹災
一般的な雹は非常に小さいイメージがありますが、天候によりゴルフボール以上の大きさになることもあります。
このような雹が屋根や天窓に落ちることでの破損の被害もあります。
雹災による被害例
雹災による被害例としては、以下のような例があります。
- 雹により天窓の窓ガラスが割れることによる被害
- 雹により屋根が破損することでの被害
火災保険を申請する際に必要な書類

保険会社に火災保険の申請をする際には、以下のように多くの書類を提出する必要があります。
- 保険金請求書
- 罹災物件写真
- 事故内容報告書
- 修理見積書
- 罹災証明書
- 損害明細書
- 住民票
- 印鑑証明書
- 建物登記簿謄本
- 保険金直接支払指図書
上記の書類の中で「保険金請求書」「罹災物件写真」「修理見積書」は、どの保険会社でも必ず提出が求められます
それぞれの書面について詳しく見ていきましょう。
保険金請求書
保険金請求書は、保険会社へ保険金を請求する意思を表明する書面です。
多くの保険会社では、WEBサイトで専用フォームを構えているのでそこに入力するか、保険会社から郵送で書類を取り寄せて記入する方法のどちらかを選択します。
記入は必ずご自身で行う必要があり、請求金額が高額の際は実印などが必要になるケースもあります。
罹災物件写真
罹災物件(りさいぶっけん)とは、災害により損傷被害を被った家屋のことを指します。
雨漏りで火災保険を申請する際には、雨漏りの被害箇所や被害の程度がわかる写真を撮影して保険会社に提出する必要があります。
雨漏りの原因の多くは屋根になるので、ご自身での撮影は危険を伴うので多くの場合は見積もり業者や修理専門業者が撮影を行います。
修理に関して応急処置に緊急性が伴う場合などは、修理の前の応急処置の写真も事前に撮影すると良いでしょう。
罹災証明書
罹災証明書とは、自然災害により住家(居住のために使用する建物 )に被害を受けた場合に、被災者からの罹災申請に基づき住家に被害が発生した家屋の調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものを指します。
自然災害の場合は、自治体に罹災証明書の発行の申請を行います。
申請する際には、身分証明書、被害が分かる写真、印鑑が必要です。
また、本人以外が申請をする場合には、委任状が必要となります。
罹災証明書には被害認定の区分が設定されており、被害の程度によりランク付けがあります。
被害認定の区分一覧
| 被害の程度 | 損害の割合 |
|---|---|
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上~50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上~40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 一部損壊(準半壊までに至らない) | 10%未満 |
事故内容報告書
事故内容報告書は、雨漏りの損害が発生した概略を報告する書面になります。
保険金請求書と同様に、WEBサイトの専用フォームからの入力や保険会社から書類を取り寄せて記載をします。
自然災害のケースでは、事故が発生した期日の特定が難しいので、気象庁などのホームページで過去の気象データを参考にして時期を絞り込むなどの方法もあります。
修理見積書
雨漏りを修理する費用を確認するために、事前に屋根の修理専門業者に見積もり依頼を行います。
修理見積書には、総額での金額の記載ではなく、修理に必要な部品など分かる範囲で詳細の記載が必要です。
火災保険での補償は屋根だけではなく、雨どいの歪みや窓の割れなども対象になることがあるので、被害箇所が広範囲になる場合などは全て見積もりを行い漏れがないようにしましょう。
損害明細書
雨漏りが起因となり、家財などに損害が発生した際の損害品を記載する書面で、保険金請求書と同様に、WEBサイトの専用フォームからの入力や保険会社から書類を取り寄せて記載をします。
住民票
住居がある各自治体にて発行します。
被害のあった住居が、実際に住んでいる場所であることを確認します。
印鑑証明書
保険金請求書に捺印する場合に必要で、住居がある各自治体にて発行します。
建物登記簿謄本
火災保険は、建物の所有者しか保険を掛けることができません。
そのために、建物を所有している方と保険を申請している方が同じ人であることを確認する際に建物登記簿謄本の提出を求められます。
建物登記簿謄本は、保険会社から提出を求められた際に必要となります。
建物登記簿謄本の発行は、最寄りの法務局で交付することができます。
保険金直接支払指図書
保険金直接支払指図書とは、賠償金の支払いを求める請求書と、修理業者に修理費用の支払いを求める支払指図書がセットになった書面のことを指します。
火災保険の保険金が銀行の質兼に設定されている場合に、保険金直接支払指図書が必要になります。
雨漏り修理に火災保険が適用されるまでの流れ

雨漏り修理に火災保険が適用されるまでには、さまざまな手順を踏む必要があります。
①保険会社もしくは、保険代理店への連絡をおこなう
まず最初に行うのは、加入している保険会社及びその保険代理店に被害の内容を説明する為の連絡をする必要があります。
可能であればこの時に修理業者への連絡を行い、被害の度合いなどを把握しておくと説明が楽になります。
保険会社に連絡した際に確認する事としては、「自然災害により雨漏りが発生しているので保険が適用できるのか」という点と、「火災保険を申請する書類を送付してもらえるか」の2点になるので欠かさず確認しましょう。
②保険会社から送付される書類の確認及び申請
前述のようにWEB及び郵送にて、保険金請求書や事故内容報告書を入手して申請の準備をします。
保険会社への保険申請には、損害箇所の写真や修理するのに必要な費用が分かる見積書なども必要になります。
保険会社に連絡する際に、修理専門の業者への見積もり依頼が済んでいない方は、ここで間違いなく見積要請を行う必要があります。
修理専門業者に連絡する際には、雨漏り修理を火災保険を適用させて修理をできないか検討している点と、その申請をする為の見積もりと写真が必要である旨の情報は開示しておきましょう。
この点を伝えることで、必要なお見積りや写真の撮影を行ってもらえます。
③損害鑑定人の現地調査
雨漏り修理の保険適用申請をした後に、保険会社が派遣する損害鑑定人が現地調査を行います。
事前に送付した現場の写真と現況に相違が無いかの確認や、雨漏りの状況が保険適用の範囲なのか見極め判断します。
④現場調査確認の結果報告の連絡をうける
現場確認の結果は、数日間~数週間程度の時間を要します。
申請の内容に問題が無ければ、保険の加入者及び申請者に保険金が支払われます。
通知が来たら修理に取り掛かるので、事前に見積もり依頼を行った修理業者と連絡を取り合い修理の時期や方法などの再確認を行います。
修理業者は保険会社が斡旋するわけではないので、ご自身で探しておく必要があります。
⑤雨漏り箇所の修理を行う
実際に雨漏りの修理と進みますが、修理する際の業者との契約は火災保険申請が下りた後に行うようにしましょう。
保険は必ず下りるとは限らないので、申請が通らなかった場合には大きな出費となるので、確認は怠らないようにしましょう。
保険の審査が通ったら雨漏り箇所の全てを修理する、逆に通らなかったら必要最低限お修理をするなど修理内容を保険の適用の有無で決めることもあるので、十分に考えて依頼しましょう。
火災保険を申請する際の注意点

雨漏りで火災保険を適用させるには、次のような注意点を守る必要があります。
保険の申請は本人のみしかできない
火災保険の申請は、契約者本人しか申請することができません。
代理申請等はできないので、修理業者などが「保険の申請まで行います」などと言ってきたら要注意です。
不当な請求や前金を取られて、その後連絡が途絶えるなどのようなこともあるので気をつけましょう。
雨漏り修理は高い技術力が必要になる
雨漏りの修理は、建物の修理の中でも特に高い技術力が求められます。
雨漏りの根本的な原因を見誤ったままで修理をおこなうと、結局数年後に再び修理をすることにもなります。
また、しっかりとした原因を特定しないと、保険適用されないなどのようなこともあります。
近年では火災保険を利用した悪徳業者の存在なども問題になってきており、修理業者の選定は注意が必要です。
雨漏りの修理を依頼する際には、過去の実績や口コミなどをしっかりとリサーチした上で安心できる業者に依頼しましょう。
雨漏りの被害を受けて3年以内の申請が必要
保険法(平成20年6月6日法律第56号)第95条(消滅時効)では、保険給付の権利を以下のように定めています。
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
この法令により、雨漏りが発生してから3年以内に申請を行わないと時効を迎えることになります。
当然ながら時効を迎えると、保険が適用されなくなります。
時効を迎えることで、本来自然災害で損害をうけて保険適用範囲内であっても、経過年数が長いと経年劣化扱いとなり保険適用外になります。
また、保険を適用する前に修理を行ってしまった場合でも、3年以内であれば火災保険で補填される可能性もあるので、保険会社に相談してみましょう。
契約している保険のタイプを確認する
一般的に火災保険には「免責方式」と「フランチャイズ方式」の2種類があります。
どちらの保険を契約しているのかで、受け取ることができる保険料が変わるので契約書をよく確認しましょう。
それぞれの方式での違いは以下のようになります。
自己負担額を決めておくのが免責方式
免責方式は、保険に加入する際にあらかじめ自己負担額を決めておく保険になります。
(自己負担額10万円での例)
自己負担が10万円の場合では、雨漏りで発生した損害額が50万円掛かった際に、自己負担は10万円になるので保険金は40万円貰えることになります。
自己負担額より損害額が多い場合には、その分多くの保険金が貰えますが、逆に損害額が10万円以下の場合には、修理費用を自分で負担することになります。
自己負担額の金額により月々の保険料は異なるので、ご自身の収入や家の大きさにより適切な金額を設定すると良いでしょう。
フランチャイズ方式は損害額20万以上の場合に貰える
フランチャイズ方式は、「損害額20万以上型」とも呼ばれ、その名の通り損害額が20万円以上の場合のみ設定した保険金の上限までの金額が貰える保険になります。
損害額が50万円の場合で、保険金の上限を50万円以上に設定している場合では、保険金は50万円支払えます。
この時の損害額が19万円の場合は、保険金は支払われません。
火災保険と火災共済は異なるので注意
雨漏りの被害を保険で修理をおこなう際に、注意が必要なのは火災保険と同様の保険に見える火災共済の存在です。
火災保険は民間企業が運営を行っており、保証の範囲や特約も複数あり安心ですが、火災共済は非営利団体が運営を行っているので、修理費用が高額になると十分な補償が受けられない場合があります。
ご自身の家計や生計の運用プランにより、どちらを選定するのか決めると良いでしょう。
まとめ
雨漏り修理で火災保険が適用される条件や、火災保険の申請の流れについてなど解説しました。
雨漏り修理を保険適用させるには、前提として自然災害である必要があります。
経年劣化での漏れや、被害から3年以上経過した場合には保険の適用範囲外になるので注意が必要です。
また、保険の契約条件によって修理費用の上限や免責の金額が決まるので、契約時によく考えて設定する必要があります。
一般的に、ご自身で屋根に上ることなどは危険を伴うのであまりないと思いますが、見ることができないことを利用して必要のない工事をもちかけてくる業者や、修理したふりをして簡易的な対処のみしかしないような悪徳業者もいます。
屋根の修理を行う際には、地域密着の安心できる業者を選定すると良いでしょう。